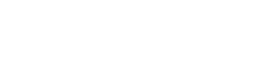好きなマンガについて 第8期 (聴講コース生) 投稿練習
A:好きなマンガ1冊のタイトルおよび巻数
「へうげもの」12巻
・作品概要
あるときは信長、秀吉、家康に仕えた武士。またあるときは千利休に師事する茶人。そしてまたあるときは物欲の権化。戦国~慶長年間を生き抜いた異才・古田織部。甲冑、服飾、茶、陶芸、グルメetc. お洒落でオタクなこの男こそ、日本人のライフスタイルを決めちゃった大先輩だ!!(Amazonより)
・12巻のあらすじ
朝鮮戦線泥沼化。キリシタン大弾圧。海外侵略と内政混乱、豊臣政権内憂外患。数奇の玉座を目指す古田織部は、わび、さびと一線を画す「乙」の境地に開眼。「めぎゅわ」なやきもので日の本を統一すべく、日夜物欲と創意をたぎらせる。日ごと病み衰える秀吉に死期が近づく。唯一の「友」として、己は何をするべきか。織部が選んだはなむけは、「贅」の男にふさわしい「祭り」であった。(同)
B:その1冊が好きな理由
本作、特にこの12巻は、何度読み返しても、その度に涙してしまう、というシンプルな理由です。今回のお題を通じ、それって何故だろう、ということについて考えてみました。
まず一つ目に思い当たったのは、登場人物の多彩さです。
戦国の世のめちゃくちゃな時代にあって、皆が必死に、しかしそれぞれが思い描く理想に向かって生きており、衝突やすれ違いを経る中で、成功を掴む人もそうでない人もいます。本作では、そうした多彩な群像の誰もが、キャラ被りしたり埋没したりすることなく、状況や心境が克明に描かれています。
時代こそ違え、同じように先行きが不透明な世界に生きる者として、登場人物の誰もが、僭越ながら豊臣秀吉の暴君性だったり、石田三成の権威主義性だったり、あるいは有楽斎の諦めの境地だったりが、もしかしたら自分の人生はこういう感じだったかもしれない、というオルタナティブとして無視できません。言い換えると、誰の人生も時代の必然であり、皆が演じるそれぞれの役割が揃って一つの時代を作っているという感覚を生じさせます。
私は読み手として未熟で、自分が直面している状況や自分を支配している感情をいったん脇に置いておいて気持ちを切り替えてから読書する、ということができないのですが、この作品は、私が落ち込んでいる時も、調子に乗っている時も、「ああ、これは自分のお話だ」と思って読める、そういう懐の深さがあり、読む度に、登場人物の誰かにシンクロしてしまうのです。
次に、笑いによってメッセージが昇華されていることです。
残念なことに、私の場合、だいぶ年齢を重ねているにも関わらず、説教をされるのが苦手です。客観的には非常に良いメッセージを発しているなと思う作品であっても、直接的な感じでグイグイこられると心のシャッターが下りてしまう傾向があります。
本作においては、その心のシャッターが機能しません。下げる間もなく懐に飛び込まれている、下げたと思っていたら裏口から侵入されている、笑いの力の前には素直に従わざるを得ない、ということを痛感します。
笑いのメカニズムには詳しくありませんが、プッと噴き出す笑い、企みに感づいた時のニヤリ、じんわりと満ちたりた時のスマイル、そうした後味の爽やかな笑いに、本作は満ちています。
三点目に、心洗われるクライマックスです。
多様な人物像で彩られながらも、本巻のクライマックスである秀吉の末期において、武将たち一同が敵対心や不満を鞘に納め、秀吉を笑わせる為に一致団結するエピソードが最高です。
天下人として栄華を極めた秀吉は、一人の人間としての悩みや葛藤を深く募らせてきました。毎夜悪夢にうなされ、死色が濃厚に顔をおおう描写。天下人へと上りつめる過程で重ねてきた業への後悔と、いずれ因果応報が我が子に訪れるだろう不安とに苛まれ、本当に自分を理解してくれる者等いないという孤独の感覚を募らせたまま、病床で寝たきりになり死期を迎えようとしていました。
そこに織部の画策で、有力武将たちが普段のわだかまりを超え参集し、最高の「瓜畑あそび」を催します。多様な人物像が描かれていることを前述しましたが、各人が時代を彩る珠玉の生き様を代表しながら秀吉の“友人”として一体となり、彼の人としての生き様に対する親愛を示します。多様だからこそ、彼らがそろって与えてくれる承認は、時代そのものからの承認であり、この上なく雄弁なものでしょう。
友人・理解者がこんなにも居たのだという驚きが、秀吉の心の壁を氷解し、死相が一転曇りのない笑顔になっていく様、真っすぐになった心で最後の最後に、織部に贈る感謝のことば。何度読んでも幸せな感情が沸き上がります。
最後に。
綺麗なことばかり書きましたが、秀吉が亡くなって程なく流星が堕ち、夜明けを迎えたそのシーンは、家康が明智光秀から密かに継いだ野心の成就に向け、遂に動き出した様子が描写されます。「瓜畑あそび」は僅かの間の演技だったというのが真実でしょう。後世に生きる我々は、やがて彼が豊臣家を滅ぼし、天下統一を果たすことを知っています。不透明な重苦しい時代であったことは間違いなく、以降、本作の描写も深刻になっていきます。
そのような時代だからこそ、秀吉の友人たちが彼に贈った救済の境地=Atonement=At-one-mentが、いっそう鮮やかに印象に残るのだろうと、そう思います。