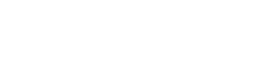好きな作品から創作の軸を考える「リンダリンダリンダ(映画)」
以前のブログで好きな作品を64作品を挙げた。
その作品群をもとに、自分が惹きつけられる要素をガーッと書き出し、ワードクラウドやチャットGPTによる分析をやってみたのだけれど、あんまりしっくりこなかったので自分の好きな作品について一つずつ考えることにした。
(好き勝手に読解しているので、感じ方が違うかたがいたら是非お話しましょう!)
【「リンダリンダリンダ」の好きなところ】
⽂化祭3日前に突如バンドを組んだ⼥⼦⾼⽣たちが、本番に向けてブルーハーツの曲を練習し、本番当日を迎える話。
あらすじはそれ以上でもそれ以下でもない。
印象に残っているシーンの一つに、部室でリンダリンダが流れるシーンがある。
文化祭で演奏することは決まったものの何を演奏するかは決まっていない。軽音部部室にあるCDを片っ端からかけて、皆が好きな曲と3日間の練習で弾けそうな曲両方を最大公約数的に満たした曲を探している中、JITTERIN’JINNの「プレゼント」のCDパッケージを見つける。
曲探しから脱線して「プレゼント」を全員で聞こうとすると、パッケージに入っていたCDの中身が違っていた。流れてきた曲は「リンダリンダ」。
偶然流れてきた「リンダリンダ」に対し、部員たちは多少戸惑いつつ、最初の「リンダリンダ〜♩」のところで、彼女らは各々のリズムで、各々のテンションで、音楽に乗る。
曲探しから脱線するし、その場のノリに支配されているわけでもない。偶然流れてきたリンダリンダに、勝手に各々のテンションが上がっている。
その様子が定点カメラでずっと映し出されている。「リンダリンダ」も演出的に音が挿入されているわけではなく、あくまで部室内に聞こえている曲として環境音的に流れる。
この映画はこの調子で最初から最後まで続く。
女子高校生たちが文化祭に向けてバンド練習をしていく中で友情を育む、、、という一応の筋はあるものの、その筋から終始脱線していく様が描かれる。
そして彼女らにとっては脱線は意図したものではない。ただそうなっているだけだ。
彼女たちが大人になって、当時のことを思い出した時、おそらく本人たちもほとんど覚えていないような記憶の断片が集積した映画だ。
この映画を好きな理由は、その脱線しまくっているところにある。
【突然の自分語り】
なぜ好きなのか。あくまで自分に引きつけて考えることが大事かなと思ったので、突然の自分語りを始める。
僕は福井県に生まれた。田舎で、周囲は牧歌的な人が多かった。
自称進学校の高校に入学したが、志望校合格のためにしゃかりきに受験勉強に励む人は少なかった。
定期テストの勉強会と称して、友達と一緒にいることが真の目的だった。会話のネタ作りとして勉強をしているような感じ。
今思えば、まさにリンダリンダリンダの彼女らのような青春が送れる環境にいた。
しかし残念なことに、高校2年の後半ぐらいから、突如この空気を受け付けなくなった。
入学以来テストの順位がほぼ最下位だったことがなんだかんだ悔しかったのか、時代の空気を真に受けてネオリベ的思考を内面化させたのか、目の前のことに打ち込むセンスがなかったからなのか、モテなかったからか、自称進学校が本気を出してきたからか、色々な理由が混ざっていたのだと思う。
とにかく、10代後半を無為に過ごすことが突如もったいないと感じ始め、受験勉強に舵を切りだした。(ちなみに、すぐに受験勉強に移るわけではなく、自己啓発本と勉強法の本を読みまくるという完全に血迷った時期を挟んでいる)
おそらくその時に、僕は牧歌的に過ごしてきた17歳ぐらいまでの人格を置いてきた。友達とストイックにカラオケに入り浸ったり、雪道を1時間かけて歩いて帰ることはなくなった。
不思議なエピソードがある。僕が「受験勉強や!」と息巻いておきながら、日課としてアニメや映画を観ていた頃(だから受験は失敗したわけだが)、けいおん!を観ていた。けいおんもリンダリンダリンダと同じく女子高校生のガールズバンドもので、日常系のアニメなわけだが、僕は最終話を観終えた時に「俺はこの空間にいることができないのか」と本気で落ち込んだ。自分も高校生で、バンドもやっていたのに。17歳ぐらいまでは物語の展開や演出にワクワクする話を好んでいたが、それ以降はむしろオフビートな物語や過剰に熱量を持った作品を好むようになった。
【まとめ】
話をリンダリンダリンダに戻す。
リンダリンダリンダの彼女たちはとにかく脱線をする。目的に囚われない。脱線を脱線とも思っておらず、日々のベタな意識に素直に生きる。リンダリンダが流れてきたからノるしかない。
今この瞬間を本気でダラダラと生きる。それは自分の17歳ぐらいまでの生き方そのものであり、おそらく17歳以降心の奥に行ってしまった生き方だ。
この映画は定点で引きのアングルが多い。カット割も少ない。
その被写体との控えめな距離感が、牧歌的な自分と目的志向でガツガツ生きる自分との距離のように感じる。その時の自分には決して戻れないことを暗に伝えられているような距離感。それは手に届かないところにある。同窓会カラオケにおける思い出の曲の熱唱はあの日々の二次創作でしかない。
目的や生産性をつい意識してしまう生き方の反対の位置に「怠惰に生きること」がある。が、それはモラトリアムだからこそ成立していたことで、競争社会に身を投じたタイミングや人生が進んでいくとその生き方は許されなくなる(という見方を内面化してしまう)。だから、ダラダラと生きていた自分がとても遠い存在になり、とても愛おしい記憶のように思えてくる。
多分もう10年ぐらいすると、自分の人生にものっぴきならないことが起こってきて、ノスタルジーに浸ることは減る気がする。この映画を好きな今の自分とも少しだけ距離ができてしまいそうな気がする。しかし少なくとも今はめっちゃ好きなんだよなぁと思い、文章として残してみました。
功利的な目的や意味に絡め取られることなく、むしろ余白や無駄こそが大事だなぁ、と感じる作品です。
、、、という感じで、自分の好きな作品がなぜ好きか、つらつらと考えてみました。
この一連の言語化の作業は、僕が物語を観る上で勝手に感じ取ってしまうアツさやエモさについての解像度を上げる作業だと感じました。
また漫画を描く合間に、好きな作品について考えてみようと思います。