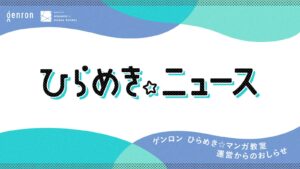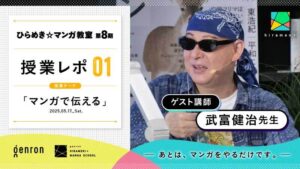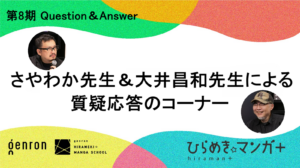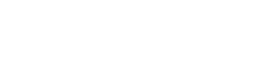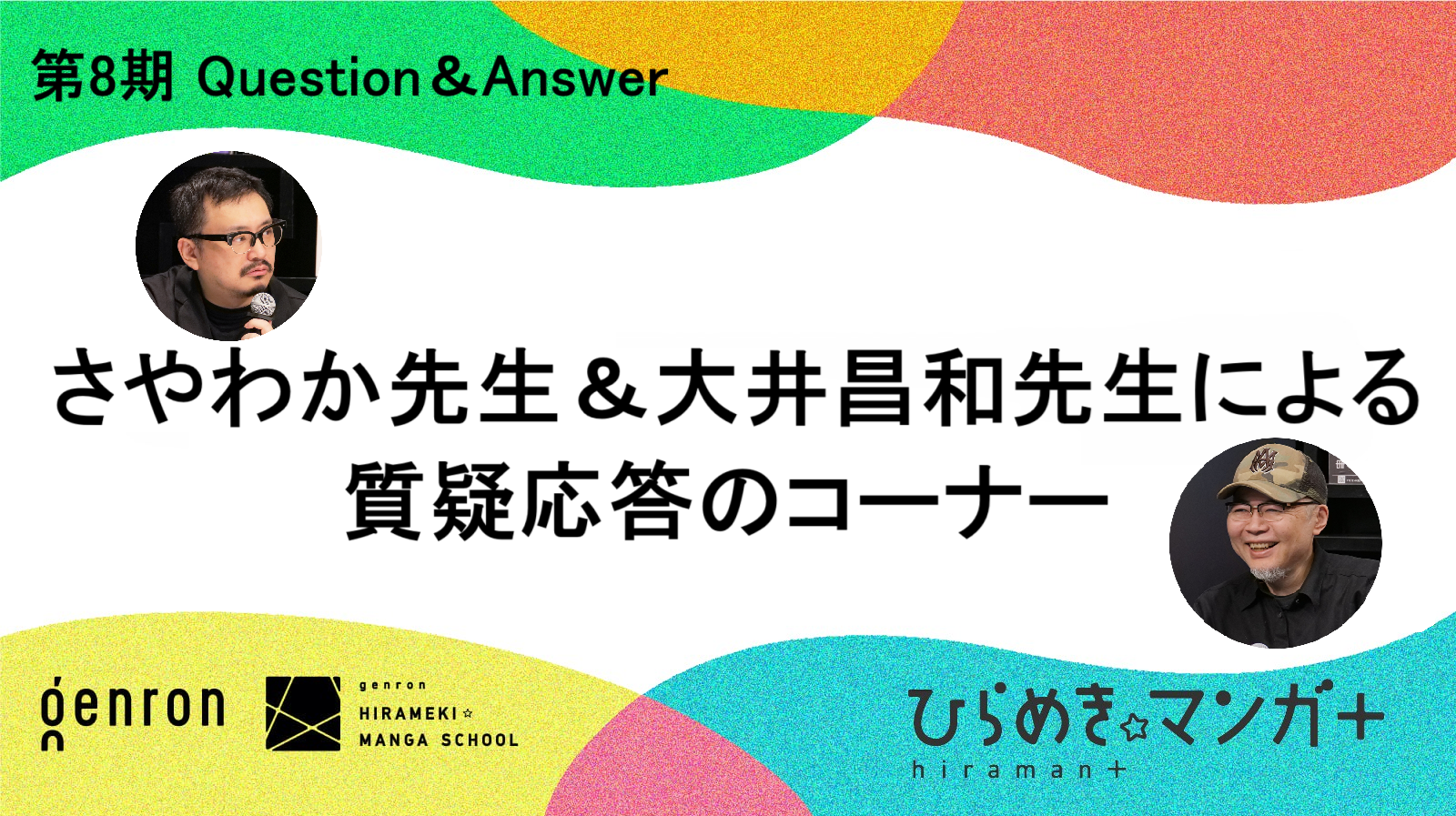
【第8期】さやわか先生&大井昌和先生による質疑応答のコーナーNo.5
ひらめき☆マンガ教室では受講生の学びを深めるために受講生専用の質問フォームを設けております。本コーナーでは「ひらめき☆マンガ+で公開可能」なものとしてフォームに投稿いただいた質問の一部を、皆さまにお届けいたします!
今回は《想定媒体の決め方とマンガを描くときのページ数》についての質問と回答をお伝えします。
質問者:きっささん
<質問内容>
1. 対象読者、想定掲載誌の決め方
実際、少年誌でリアルな描写や過激な描写が多い漫画や、青年誌で小中学生にもウケるようなポップな漫画もあるかと思います。
また、少年誌や青年誌等の中にも種類があって、各雑誌の特徴をよく理解できてないのですが、どのように想定していけばいいでしょうか。
- 16ページの漫画と30ページ以上の漫画の違い
課題では最大16ページとされてますが、新人賞の受賞作は30ページ以上の漫画が多いと思います。
どう描き分けたらいいかわからず、16ページに詰め込みすぎてしまったり30ページ以上で描いたときに間延びしてしまったりしそうです。
それぞれどう考えて描けばいいでしょうか。
既に触れた内容あるいは後の授業の触れる予定かもしれませんが、ご回答いただけますと幸いですよろしくお願いいたします。
<さやわか先生からのご回答>
きっささん、ご質問をありがとうございます!ふたつのご質問をいただきましたので、それに沿って以下にご回答差し上げますね。
まず、””1. 対象読者、想定掲載誌の決め方””について。「少年誌や青年誌等の中にも種類があって、各雑誌の特徴をよく理解できてない」とのことですが、これはぶっちゃけ、読むしかないと思います。自分が把握できていないなら、一個一個把握するしかない、というのは、まあ当然ですよね。
おそらく、きっささんが気にしてらっしゃるのは、「全部見るなんて、そんなの大変じゃないか」ということだと思います。しかし、別に全部見る必要はないと思います。ざっくり、各媒体をバラバラっと眺めて、どんな絵柄の作品が多いか、どんなジャンルの作品が多いか、ランキングに入っていそうな、一番人気がありそうなのはどんな作品なのか、みたいなことを確認するだけなら、そんなに時間はかかりません。最近はネットで無料で読めるケースも、安くサブスクで読めるケースも増えましたから、そこまで難しいことではないはずです。
ついでに言えば、画面の印象の白さ/黒さ(つまりページ内のベタの量)を見て、なんとなく読者傾向を把握するとか、その媒体に掲載されている広告を見て、どういう読者がいるのかを知るとか、SNSや掲載サイトの読者コメントを見て、読者傾向を把握する、みたいなことも、よくやられることだと思います。
しかしこうしたそれぞれの手法が重要なのではなく、大事なのは結局、「一個一個見ましょう」ということです。「スペリオールは最近勢いがあるよね」「あそこの媒体は最近あれが売れてるよね」みたいなことをひらめき☆マンガ教室の講師陣はたまに言いますが、それも、日々掲載媒体をざざっとチェックしているからでしかありません。今から商業媒体で仕事をしようとなさっているのであれば、その商業媒体ってのにどういう作品が載るのか知っておくことは、当たり前ですが必須です。しかも、自分と同じ、新人作家予備軍のひとたちは、それを怠っていたりするわけです。だったら、それさえやっておけば、ライバルたちの中で抜きん出た存在になれるかもしれないですよね。そんなわけで、ちょっとずつでもいいですから、各媒体の傾向を把握していけばいいんじゃないかと、僕は思います。
次に、””2. 16ページの漫画と30ページ以上の漫画の違い””について。マンガの原稿は、基本的に「ページ数」を最初に想定すべきだと、僕は思います。つまり今から描くのが16ページなのか、あるいは30ページ以上なのかを想定するところから、アイデアやプロットやネームを構想すべきだということです。
こと商業マンガだと、特にそう言えます。なぜなら、商業マンガは掲載誌(または単行本)の紙幅が決まっていたりしますし、締め切りまでに描ける作業量から逆算して仕事をしなければならないからです。極端に言えば、100ページのネームを思いついたとしても、提出の締め切りまでに3日しかなければ、そんなものは描けないし、そもそも描かない、と判断すべきだということです。
なので、まずはページ数を決めます。そうするともう、最初の時点で、いろいろと、作品内でやれることや、やれないことが「決まってしまう」わけです。ひらめき☆マンガ教室の受講生には、たまに、長い話の「全体」を圧縮して、無理やり16ページにおさめる、みたいなやり方をする方がいらっしゃいますが、それはちょっと間違っていて、そもそも16ページなんだから、長い話にしないし、シーンの取捨選択を最初から行って、優先順位の低いシーンははじめから描かない、ということです。
マンガを描くのに慣れてくると、いろんなページ数の経験を積むので、16ページと言われたらこのくらいだなとか、32ページならこういう話が描けるなとか、物語のサイズ感がわかってきます。まずは受講生のみなさんには、その「16ページのサイズ感」をわかるようにしていただきたいのです。なぜなら、少ないページ数からシーンを増やすことは、デカい物語を思いついちゃって、それを無理やり削るより、ずっとたやすいことだからです。
というわけで、まずは少ないページ数でも物語として成立するものを描き、30ページ以上と言われたら、最初に削り落としたシーンを復活させたり、細かな芝居や演出にコマ数を増やすような処理をしつつ、増やしていくのが、学び方のルートとしては正攻法かなと個人的には思います。
以上、いただいた2つのご質問へのお答えとしては、そんな感じになります。もしよろしければ、何かの参考にしていただければありがたいです。
<大井先生からのご回答>
きっささん、ご質問ありがとうございました〜。二つご質問あるので①の方から答えさせていただきます。
まずは①の媒体の理解の仕方からの対象読者・望む掲載媒体のご質問から。こちらはご質問の文章を読むと、媒体の特殊事例、例外的なものを取り出して問題にしてるように感じました。青年誌の中にポップなもの、少年誌の中に青年誌ものっぽい作品があるのは、それらが多数派でないということですよね?であれば基盤にそれぞれ青年誌少年誌があるので逆張り的に存在するものだという例外であろうと考えられます
であれば、
ポップでない青年誌
青年誌ぽく無い少年誌
の方を考えるだけで良いと思います。
②のご質問の方ですが、おっしゃる通り16pと30p以上は内容や書き方が変わります。がしかし、書くということは変わらないということです。書き分けるというのはまず、16pで書けるものは何か、が理解できれば16pは書けるということですし、同時にそれは16pで書けないものがわかるのだと思います。なので30pのものを書こうと考えた時に、この内容は16pだなとわかっていればその内容は少なくとも30pに合わないことがわかるわけです。
では16pと30pの違いは何かといえば、そのページ数内の起伏の数です。起伏は読み手の感情の起伏です。それは数であるし起伏の幅でもあります。この起伏をコントロールすることこそ表現の学びであると思います。30pは16pよりこの起伏のコントロールが複雑になるということですので、まずは16pでそれを学ぶというのは自分は理に適ってるな、とかんがえてますし、これまでの教室でこのページを見直されていないことから見ても、悪いページ数でないという経験が重ねられているということだと思っております。
以上です!
本コーナーは不定期配信です。
更新があった際にはSNSなどでも通知いたしますのでぜひお読みください🌴
おわり