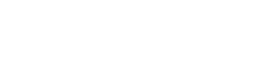好きなマンガ: 黒田硫黄「茄子」について ――偶然のソウカイ感
(一応ネタバレに配慮します。記事中で「茄子」のラストシーンについて書きます)
好きなマンガとして黒田硫黄の「茄子」を挙げます。
巻数は一巻にしますが、同じようなフンイキだし、どれでもよかったです。
基本的なデータは
講談社/アフタヌーン/連載2000ー2002/全三巻
切れモノ(続きものでない)の短編集のようなもので、各話に、
・田舎に引退し茄子を栽培する男
・自転車レースの選手
・地方で不倫するトラック運転手
・卒業のあと無職の男女
・親の会社がつぶれてしまった女子高生
……などの話が入っています。
それぞれが別の話ですが、たまに話をまたいでつながったりします。何度も話に出てくる人物も、一度きりのもいます。
(ただ、どの編にも、必ずナスが出てくること、ちょっと社会からあぶれた人々という共通点があります)
***
はしょって言うと、他の多くのマンガと違って、人物の役割がそんなに決まっていなくて、自由に動いているので、爽快感があり、よいマンガ……というのが今のところの感想です。
サクッと終わらせるつもりでしたが、こっから長い分析をします。読んだことのない人には面白くないかもしれません。たぶん。
(長文だし、チョットかったるいので、しばらく、ですます調をやめます)

***
たとえば、ひとつの話を要約しても(一巻「ランチボックス」)
「高校を卒業して、働かず、ブラブラしている男女が、キャッチボールをして、外で昼のお弁当を食べる話」
できごとを要約しても、まったく面白さが伝わらない。
二人の男女はキャッチボールをしながら、にこやかに
「わたし レンアイとかケッコンとかしないで生きようっと」
「だよな。俺もそうしよう」
などと会話する。
珍しくてよいシーンだったが、そのよさはセリフだけで成り立っているものでもない。
ただ、このマンガには、キャラクタたちが、どんなセリフでも言える大らかさがあって、そのフンイキが、何から発生しているのかが気になった。
マンガの要素を観察してみた。
***
多くの話に、三、四つくらいの特徴がある。それらが微妙なバランスで、ヘンな世界観を生んでいる。
(たぶん「客観的」よりもさらに突き放したもの。言葉が分からないが、偶然世界観のようなもの)
それがきっとオモシロい……というか異質だと思いました。
特徴は以下(ホントはマンガの画を引用したかった。でも引用していいか分からないのでやめときます)
1) 絵のテキトーさ
たぶん、少しザツに描いている。ワザとだと思う。
描いてあるものが分かりにくいことはない。線がハミ出しているとか、ちょっと形が変とか、その程度。
2)人物のビジュアルは深刻でない
深刻なカオの造型でなく、表情もカラッとしている。ユーモラスなことも。
3) ズレとユーモア
ここがキモだが、説明しにくい。ヤッカイ。
マトモな話のつくりから適度にズレている。
(「適度に」なので、あんまりズレているとデタラメになってしまい、合いすぎるとフツウになる)
たとえば「ランチボックス」はだいたいこんな感じで進む。
学校を卒業して、すぐ仕事をやめ、ゲームとかやってた女子
→ゲームに飽きて散歩に出かけると、ウサギを抱えた元同級生の男子に会う
→二人とも仕事をやめたのだ
→あ そうだ あさってキャッチボールしようよ
→あ そうだ 弁当とか作っていこう
……
無職の若者だから、時間があるし、キャッチボールをしてもおかしくはない。その時に弁当を持っていっても変ではない。だが、思いつくタイミングが唐突で、二人とも無職ですることがないことに対し、非常にほがらかだ。
そんなゆるいズレがあっても、絵が微妙につながっていたり、またズレたこと自体によるおかしみもあり、絵の雑さ、ビジュアルも手伝って、読めてしまう。
話だけでなく、絵自体・セリフと表情・大ゴマの使い方も変わっている。
偶然撮れちゃったようなショットが多く、セリフと表情が少しズレたりし、何でもないできごとを大きく映したりする。
それで、言動もできごとも、偶然に見え、ユーモラスになる。
(口語を崩しているのも、フンイキをまろやかにする。
「おなか減んない?」「あ おいし」「どーすっかねー」「もっかい言って」
さらに崩して
「忘れった」「あいっす」「それはあ」「ぬに(何)ー!」「べんとお(弁当)」など)
***
モノローグも少ない。
彼らはすべて外に話してしまう。あるいは、思案しているような画は出るが、内容は不明のため、言うことが唐突に見える。
人物たちの心理は不明になり、セリフが勝手に口から出た感じになる。
(けなす意味ではないが、何だか、フキダシが、人物から出た屁のようにも見えてくる)
行動も(他の短編では、誘拐も殺人もある)好き勝手やって、カラッとしたカオだ。
***
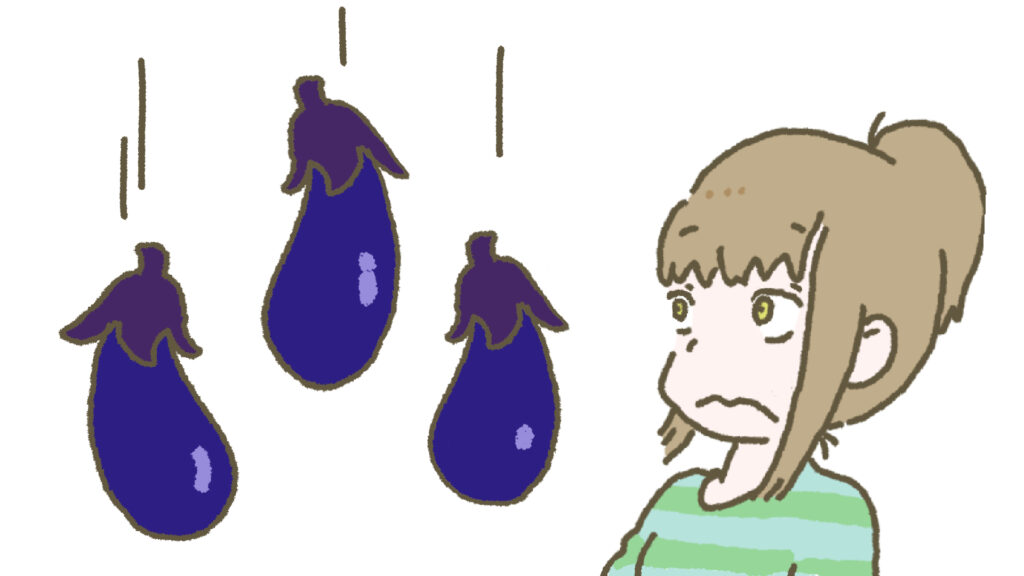
ゴチャゴチャ観察したが、ようするに、大人を奔放な子どものように見せるために、こういう描き方になっているのだと思う。
ほがらかさ、ちょっとズレた言動のユーモア、ヘンな言葉遣い、偶然な思いつき、唐突感、深刻でない……
それらの特徴が、元気な子供に見えるので、それで大らかに……というか、
「人物たちがコチャコチャやっているが、元気でいいわね」的な視点で、心理をあまり気にせず話を読むことになる。
慣れてくると、大らかで、ここちよくなる(はじめて読むときは違和感がある)
子どもは、言っていることが少し変でも放任される。
行動が変でも、少し変な遊びをしている程度になり、つまりキャラクタはある程度、自由なふるまいが許される。
(といっても、描く方は微妙にバランスを取りながら、自由に見えるように描いていると思う)
***
とはいえ、その視点は見かたを変えれば「人物が色々いて、色々やっているが、すべて偶然的でタイシタことはない」にもなる。
最終巻のラストの三コマの終わり方が面白い。
*
田舎で茄子を栽培していた男。家の庭に小さな木の苗を植えた。
次の大ゴマで、それはアッサリと大木に育つ。家は廃墟になっている。
最後のコマで、農機具に乗った人々の会話
「昔はここの木のところまで人が住んでたんだ」
「じいちゃんもういいよ。昔のことは」
で終わり。
それまでのキャラクタたちはアッサリ失せ、エンドになる。
木が育ってエンド、の作品は他にもありますが、あまり気にされずにサクッと終わるのは、珍しくて、自分には逆にソウカイ感がありました。
別のヒトが読めば、何じゃそら、かもしれませんが……
(でも、何だかあまり「茄子」のよさが伝えられなかったと思います。マンガの絵を引用せず、伝えるのは難しいです。それによく考えたら、そんなに好きなマンガでもないのかも……でも気になるマンガではありました)

***
「茄子」は万人向けのマンガではないので、他に好きな、有名なマンガとかも書いておきます。
(プロフィールにも書きましたが)
名作:
「火の鳥 宇宙編 生命編」 手塚治虫 (けっこうサスペンスがあって怖いです)
「洗礼」 楳図かずお (これもホラー……と言っていいと思います。強引に話が進む感じがいいです)
「寄生獣」 岩明均 (構成に無駄がない。岩明均のマンガは他もハズレがないです)
変なマンガ:
「必殺するめ固め」 つげ義春
「モヒカン族の最後」 杉浦茂
「私はバカになりたい」 蛭子能収
長新太のマンガ
(すべてシュールなマンガです。興味があればどうぞ)
最近のマンガ:(群像劇も好きです)
「スキップとローファー」 高松美咲
「天国大魔境」 石黒正数
「大奥」 よしながふみ(まだ全部読めてませんが、たぶん面白い)

終ハリ