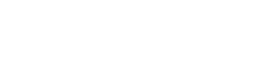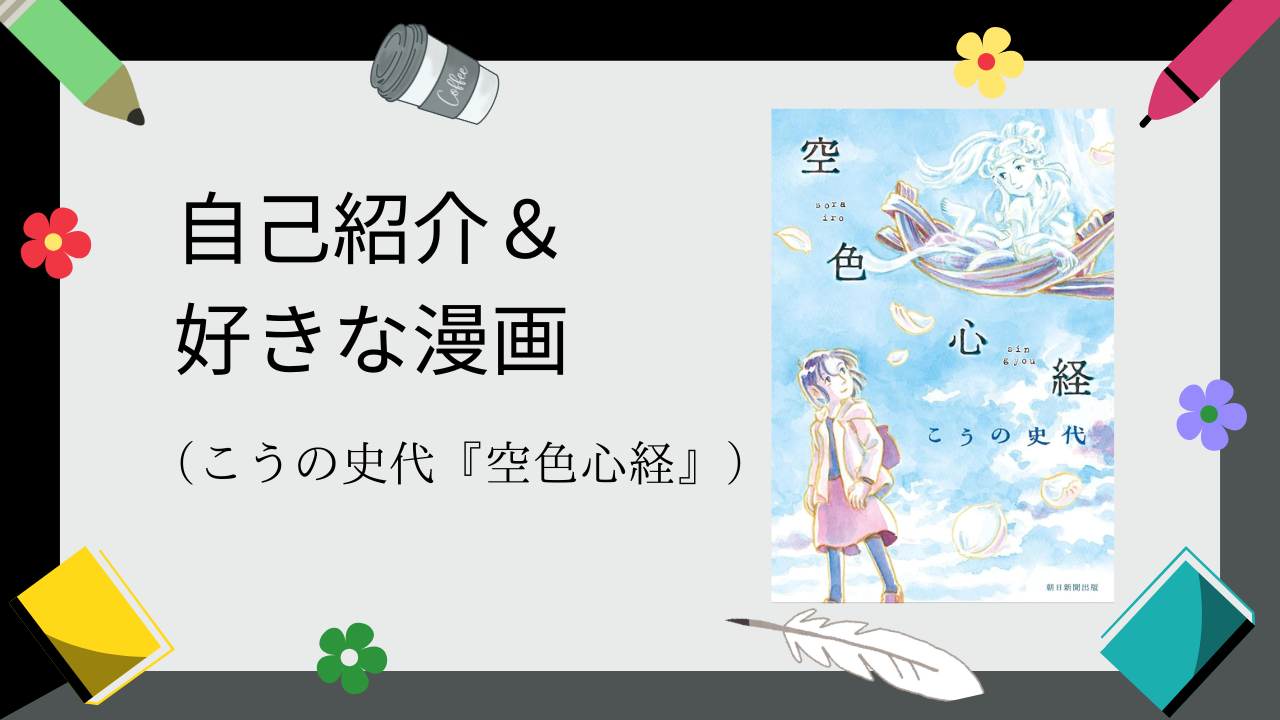
自己紹介&好きな漫画(こうの史代『空色心経』)
自己紹介
8期聴講生で参加します環田かんと申します。
過去に教室と関係ない人間として、課題提出作の感想を勝手に書いてnoteにあげたりしたこともチョットだけあったのですが、今期は聴講生としてマジで、マジで感想とかその他いろいろを書いていくよって所存です。よろしくお願いします。
好きな漫画を一冊
好きな漫画一冊は、こうの史代『空色心経』を挙げます。最新作ですね。
こうの史代作品で一番好きなのは『長い道』なのですが、最近読んだ『空色心経』が良い漫画だーっと感動したのでこれについて書いてみますよ。
物語はコロナ禍で夫を亡くした主人公の女性の話の現代パートと、観自在菩薩(観音様)が舎利子(シャーリプトラ)に対して語る般若心経の話のパートの2つが同時に進行します。最終的に女性は夫の死と向き合い乗り越えることとなり、そこに般若心経が関係してくるよって話です。般若心経!お坊さんが唱えるやつですね。私はわりと好きです。眠ってもよい時においてはですが。
『空色心経』は二色の線で描かれている漫画でして、コロナ禍の現代パートは黒の線、般若心経のパートは水色(空色)の線で描かれています。そして般若心経のパートは非現実的な世界として描かれています。
この二つの世界、つまり彼岸(あの世)と此岸(この世)は基本的には交じりあいませんが、物語の後半に主人公が夫の死と向き合うにつれ画面の中で二つの世界の”線”が交じりあっていきます。交じりあうといっても物語上、現実世界に非現実的な世界が入り込んで曖昧になって……みたいなことではありません。
作中世界内では現実世界は現実のままで交じり合いませんが、漫画の”画面上”では現実世界の黒い線に混じって水色の線が描かれていることで、二つの世界が交差していることを表しています。いや、交差というよりは彼岸と此岸が隣り合わせになる、重なって存在しているといったほうがよいかもしれません。
『空色心経』の最後の見開きページでは亡くなった夫のことを思う主人公が「案外近いんかもな」と呟いて眺めた風景が黒の線と水色の線が混じった形で描かれています。この風景にまさに主人公が身近な人・大事な人の死と向き合うという苦悩を乗り越え至った(悟った)心境が表現されており、物語の締めとして見事ですし、感動すしました。
『空色心経』においてなぜこのような表現が可能なのかといえば、こうの史代が線の集合(ベタ塗りではない)によって作品世界を形づくる作家だからです。
そもそも漫画自体が線によって世界を創造し物語を動かすメディアですが、こうの史代はそれを突き詰めており、線の集合とその密度によって風景を描き、そこに”日常”世界の微妙なニュアンスの変化(哀愁とか郷愁とか、あるいは侘び寂びといえるかも?)を表現していると私は思っています。すべてが線で表現されるから、「異なる世界が重なって存在する状態」も二色の線で描くことができるわけですね。
途中、観音様が「空(くう)」の概念について説明する箇所がありますが、その際に観音様は、「世界は空間に連なるマス目で構成されており、事物はマス目にその瞬間に宿る(マス目を塗りつぶしたり塗りつぶさなかったり)虚像でしかない。だからすべてに何も意味はない。一切は”無”である」といった意の説明をします。これってこうの史代の漫画そのものを説明している箇所じゃん!自己解説してる!と興奮しながら読みました。線で描かれた虚構の”日常”はそれ自体が”無”でしかないですが、時間や次元を超えて誰かに届き、なにか意味のあるものになるかもしれない。漫画は紙の上にイチから虚構の世界を描くものですが、私たちはそれを読んで感情を動かされ、時には勇気をもらったり癒されたりします。虚構は現実ではないですが、現実に常に重なりあって存在しているといえると思います。『空色心経』は物語で一人のキャラクターを救うと同時に、二色の線によって描かれた絵によって虚構が現実の私たちにとって救いになり得ることを説明しているのですね。
要は、この作品すげえ!感動した!好きだ!金沢でやってるこうの史代展に行きてえ(唐突)ってわけです。
漫画の説明とか慣れてないくせに長々と書いてしまいましたが、今後漫画の感想などはもっとわかりやすくコンパクトに書いていきたいです。本当は私が一番好きな『長い道』に通じるような要素も『空色心経』にはあって……みたいなことも書きたかったのですが、収拾がつかなくなりいつまでもこの文章がサイトにアップできなくなるのでやめました。
とにかく完成させるのが大事!ということで、聴講生の立場ですが1年間よろしくお願いします。