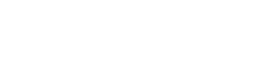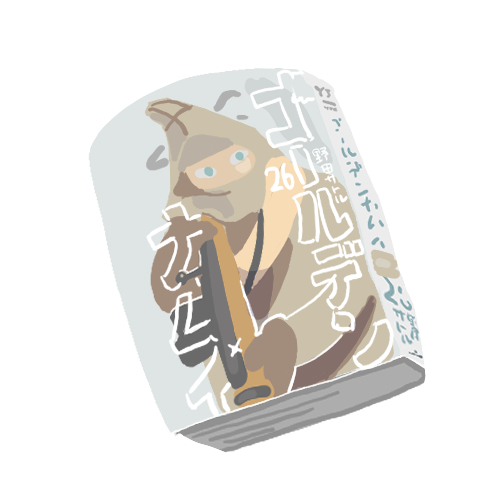
『ゴールデンカムイ』26巻 8ページ分の惨殺シーンから考える「救い」のかたち
私の好きな漫画
こんにちは。8期制作コースの宇佐木とかめです。
今回は、好きな単行本1冊についてお話します。
私が惹かれる主人公像は「何かに深く蝕まれている人」です。
他人の理解が及ばないような経験にさらされ、その傷を抱えたまま、それでも前に進もうとする。
そういうキャラクターを見ると、私は強く心を動かされます。
彼らの姿に触れると、「これは自分にもあった感情かもしれない」と気づかされることがあります。
そしてその感情が、物語の中で途中で断ち切られず、最後まで描ききられているとき、私はそこに「救い」を感じます。
死や絶望を出発点にしながら、生への肯定にまで昇華していく過程を見ていたいです。
この視点から特に心を打たれたのが、以下の4作品です。
• 『ゴールデンカムイ』26巻(野田サトル)
• 『邪眼は月輪に飛ぶ』(藤田和日郎)
• 『骨の音』(岩明均)
• 『平和の国の島崎へ』1巻(原作:濱田轟天/作画:瀬下猛)
これらの作品に登場するキャラクターは、辛い過去を背負いながらも、それを同情の材料としては扱いません。
痛みや狂気をきちんと描いたうえで、読者に寄りかからない。
だからこそ、彼らの強さがまっすぐ伝わってくるのだと思います。
そのなかでも、とくに私の心を捉えて離さなかったのが『ゴールデンカムイ』主人公の杉元佐一でした。
次に全31巻中なぜ26巻なのかご紹介します。
2つの視点から見る8p分の惨殺で描かれる「救い」
26巻の中でも最も印象的だったのは、連続娼婦殺人事件の犯人を杉元が8ページかけて惨殺するシーンです。
未読の方のために補足すると、この場面はいわゆるバトルシーンでは決してなく、杉元(と仲間)が一方的に加害する暴力の描写です。
青年誌では暴力表現は珍しくありませんが、このシーンの“量”と“質”は、突出して異常です。
にもかかわらず、この8ページには、私にとって明確な「救い」がありました。
それは、2つの視点が同時に成立していたからです。
1つ目は、読者の感情を代弁する「主人公キャラ」としての杉元の視点です。
現実でも見過ごされがちな「女性」「性労働者」という存在に対する暴力が、作品の中では杉元によって徹底的に裁かれます。
その構造に対して、男性誌なので荒々しい展開が来ると構えていたところに思わぬ展開がきて、心に沁みるものがありました。
暴力の是非とは別に、「こんなにも他人の痛みに本気で怒る人がいる」
その事実に、私は救われたのだと思います。
2つ目は、杉元というキャラクター個人の動機の一貫性です。
もし彼を単に「主人公」として見るなら、「なぜ急に正義を振りかざしたのか?」という疑問が生まれます。
けれど杉元を“ひとりの人間”として見たとき、彼の怒りには明確な理由があります。
杉元はこれまで、死刑囚の皮を剥いで収集するという旅路の中でも、決して相手を「ただの怪物」として処理せず、“人間”として向き合ってきました。
それは、「自分の人生は自分で選び取ってきた」という彼自身の覚悟があるからこそ、できたことだと思います。
だからこそ、自分の出生を言い訳に殺人を繰り返す今回の犯人に対して、ガチギレした。
これは一時的な感情ではなく、杉元という人物のこれまでの選択と倫理が積み上げた、必然の行動だったと感じました。
この場面には、『少年誌に求められるヒーロー的な行為』と『青年誌が描く業を背負った人間のリアルな感情』の両方が同時に成立しています。
だからこそ、私はこの8ページを「納得できる暴力」として受け入れられ、むしろ救われたのだと思います。
最後に
この課題を通して、私はあらためて「蝕まれた人間が、それでも生を肯定していく姿」に強く惹かれていると実感しました。
そしてその感情は、ただモノローグで説明するのではなく、キャラクター同士のやりとりや行動の積み重ねによって見せていくことが大切だと感じました。
ひらめき⭐︎マンガ教室8期を通して、この課題に少しずつでも解決できたらと、頑張ります。
宇佐木とかめでした。