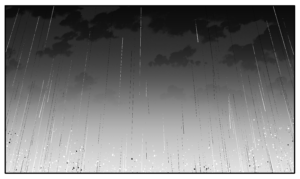【WS】かわじろう『吉野山の話』感想文
https://school.genron.co.jp/works/manga/2022/students/jirooo/25352/
かわじろう『吉野山の話』
物事は光を受けることなく存在することはできない。
このマンガはモキュメンタリーだ。とある新人力士が遭遇した不思議な出来事を追いかけている。
現実の固有名詞や出来事を織り交ぜつつ、不思議な話を描いてみせる話運びは見事なのだが、ここではある画面表現にこそ注目したい。
最後のページ、最後のコマにだけ陰影のトーンが貼られている。
(4ページ2コマ目や土俵にもトーンが貼られているが、前者は演出、後者は質感表現なので陰影のトーンではない。)
作者のアピール文に、
<「相撲らしさ」を作っている要素のひとつに、力強い黒色があると思います。漫画の画面上でも黒色が力強く見せたいと思い、黒色ができるだけ高いコントラストで見えるようにトーンを極力使わないことにしました。>
とある。
なるほど、力士の肌に対して髪の毛、まわしの黒色のコントラストが「相撲らしさ」を表現していて、狙いのある画面作りが効いている。
(強いて言えば、女将さんの服には色をつけてもよかったのではないか。裸の力士との区別がつきやすくなる。)
中間色を抑えるからこそ、暗闇パートの表現も際立つ。
線とベタのみで表現されていた人物に対し、鉛筆を寝かせたようなブラシで描かれたおばけ力士に異質な存在感を感じることができる。
<トーンを極力使わないことにしました>という作者の意図と、画面表現が一貫してかみ合っている。
では、最後のコマに使われた陰影のトーンはなんなのか。
単に形や状況を説明しているのではない。この陰影のトーンこそが、荒唐無稽な話が現実に接近し、モキュメンタリーに変貌する読後感を演出している。
写実的であれ記号的であれ、どんなマンガでも描写のレベルが常に一定ということは少ない。決めゴマでは描写の密度が上がる。
むしろデフォルメの強い画風のほうが、描写のルールが変わった瞬間の記号のずれが読者に強い印象を与える。
個々の陰影の描き方だけに注目すると、そこには様々な効果がある。
たとえば、地面に長く伸びた影や、真横から光を受けて頭の側面が暗くなっているキャラクターの絵を見ると、読者は情緒を感じる。
これは、太陽の位置が低い時間帯の光の当たり方であり、西日、夕方のドラマチックな情景を思い起こさせるからだ。地球上に生きる全ての人間の感覚にすりこまれている、光の表現のセオリーである。
ただ、全てのコマにわたって細かく陰影をつけても効果は薄い。
コマ割りや台詞の量と同じく、描写もリズムによって効き方が変わる。
一貫して色数を絞った表現から、最後の最後に陰影のトーンで光を表現することにより、記号のルールがほんの少しずれる。作者によって巧みにずらされたこの瞬間に、不思議な話の意味が一変する。光が当たり、記号のルールが現実に接近し、そのまま終わりを迎えることで読後感が描きかえられてしまう。「こういう話が本当にあったのかもしれない」と。
表現の効果を言語化できずとも、読者は不思議な読後感を覚えることができる。それこそが「絵で伝わる」、そして「リズムで伝わる」ということであり、マンガ表現の醍醐味だ。
暗闇に現れるおばけ力士に土をつけた翌朝、吉野山は光を受ける。
光は画面左から当たっている。日本の見開きマンガは右から左に読み進められる。読者の目線が進む方向から当たる光は、吉野山の表情、ナレーションとかみ合い、キャラクターの進む道のりが前向きであることを予感させる。光を受けた吉野山は、二度とおばけ力士と出会うことはなく、別のステージへ進むのだ。
表情の塩梅も心地よく、黒白の二色から一色足された画面からは、視覚で伝わる以上の実感を覚えてしまう。力士とすれ違ったときに鼻をくすぐる、髷を結うための鬢付け油の甘い香りすら漂ってくるようだ。
わたし自身もマンガ家であり、日々制作に苦悩している。
自分のやっている細かい作業に意味はあるのか?と不安になることもある。そんなときは好きなマンガを読み返して元気をもらう。
わたしにとって『吉野山の話』は、読むたびにマンガの面白さを思い出させ、マンガでできることはたくさんあるのだと勇気をくれる作品のひとつだ。